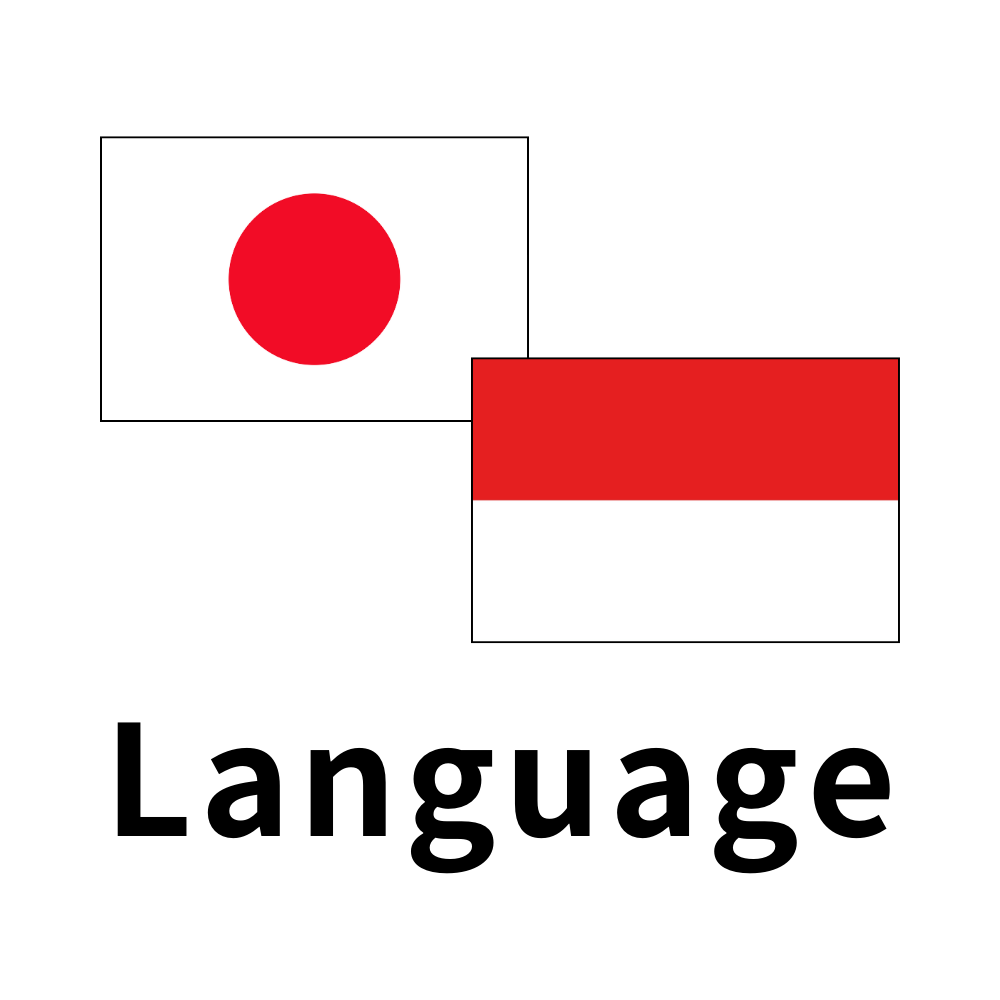第10回定例研究会は、当プラトニックフォームの研究統括であり株式会社CONVI代表取締役の鍋島祥郎が日本で発表されている外国人に関する統計において移民労働者の実態がどのように把握されているかを報告しました。
■どんな統計に外国人労働者は捕捉されているか?
まず日本の統計で外国人または外国人労働者が捕捉されているのは「国勢調査」「住民基本台帳」「出入国管理統計」「雇用統計」の4つです。国勢調査に見る外国人は第5回定例研究会の水内先生(大阪公立大学)のご発表で地域ごとにどのような在留資格と国籍の外国人が集中しているかが全然違うことが詳しく述べられていましたが、このほかに国勢調査データが興味深いのは、国籍別に人口ピラミッドが確認できるので、どの国籍の人がいつ頃どのような経緯で日本に移民として入国し、定着してきたの経緯が推察されることです。
■住民基本台帳
住民基本台帳は各自治体が住民の転出入の記録を統計として公表するものです。日本全体では外国人は転入超過であることがわかりますが、自治体別にみると転入超過は東京だけで、3大都市圏で見ても大阪はよこばい、名古屋は転出超過となり、外国人においても東京一極集中が起こっていることがわかります。
■出入国管理統計
この統計が文字通り外国人の出入国の記録を公表するものです。入国数はこの20年間どんどん増加していることは明白ですが、明治以降の出入国の統計により、時期によって入国する国籍は偏っており、特定の国との関係と日本の移民労働政策が密接に結びついてきたことがよくわかります。特定技能の創設によって多少オープンな移民受け入れが進んできておりますが、明確に外国人移民の受け入れを標榜していない日本においては労働力需給を特定の国との外交関係によって調整を図ろうとして来た経緯がよくわかります。
■厚生省・文科省統計
厚生省は労働行政の基盤とするために雇用者の統計をとっており、その中でも国籍別の雇用者の捕捉がなされてます。産業別の集計ができるので、国の外国人施策がどの産業にどのような影響を及ぼしているのかその効果を確認することができます。注目すべきことは、特定技能の創設以前の10年間に技能実習制度の改正による急激な人口増ののち、コロナ禍の前にすでに頭打ちがきていたことです。ちょうどコロナ禍のタイミングで特定技能が創設されていますが、その政策効果を見極めるのはまだ時期尚早のようです。
また文科省は外国人留学生の統計をとっていますが、日本への留学生の導入はコロナ禍以前の状況を回復できておらず、明らかにコロナ禍を経て日本離れが進行しました。特に大学と専門学校の停滞が顕著です。
■世界の統計
最後に国連の移民統計によって、いま世界では労働力のグローバル化が大きく展開していることがわかります。特に先進国間の労働力移動は大きく、世界は労働力シェアの状況にあり、人材は国境をこえて就職先の選択を行っています。その中で日本は依然として開発途上国からの人材受け入れという旧来型の構造であることがわかります。今後の日本の労働市場のグローバル化がどのように進展するのか、今後の政策が注目されるところです。